メディア案内|データ復旧
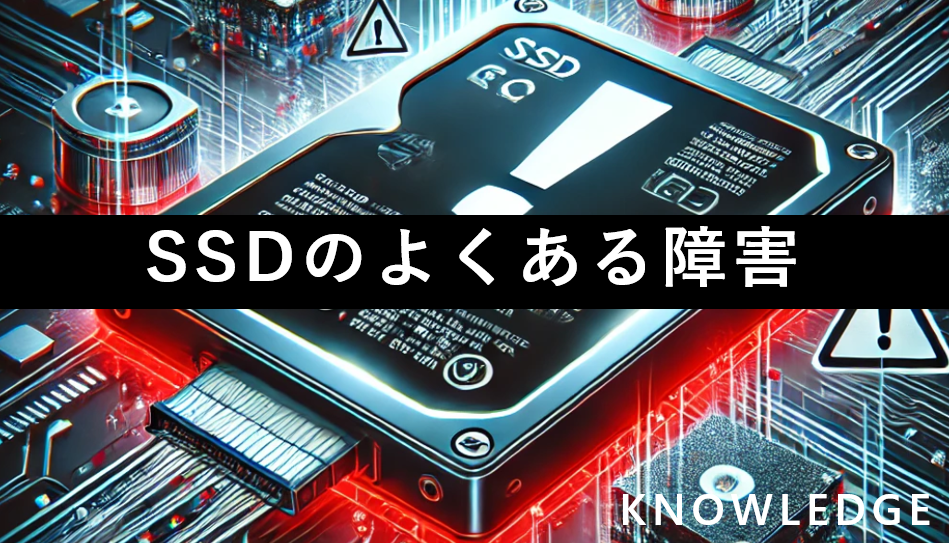
SSDのよくある障害・故障|データ復旧
SSD(Solid State Drive)は、基板上に複数のフラッシュメモリを搭載し、データの読み書きを並列で行う仕組みを採用しています。そのため、1つのフラッシュメモリが壊れるだけでも、データの読み取りが困難になります。さらに、フラッシュメモリは通常、同じロットのものが複数搭載されているため、1つのメモリに不具合が発生すると、他のメモリも同時期に問題を起こすことがよくあります。
フラッシュメモリ自体は精密な電子部品であり、電気的なストレスに弱く、水没などの水によるダメージも故障の原因となります。障害が発生したSSDからデータを復旧する際には、場合によっては基板からフラッシュメモリを取り外す必要があります。ただし、フラッシュメモリの接点がモールドされている場合、メモリの取り外しは困難であり、データ復旧が一層難しくなります。
論理的障害
論理的障害とは、SSDに保存されているデータが破損することで生じる障害を指します。誤ってフォーマットを行ったり、データを削除したりといった誤操作によるものを論理障害と呼びます。また、SSDに書き込まれている構造情報(例えるならば、1冊の本で例えるならば、目次のようなフォルダ名やファイル名の情報)が、OSの不具合などにより破損することもあります。
ファームウェア障害
ファームウェアとは、SSDを制御するためのソフトウェアのことです。以下は、ファームウェアに関連する主な障害例です:
- メディア容量の誤認識: SSDの基本容量が破損し、本来の容量が256GBや512GBであっても、8MBなどと誤認識される不具合。
- 時間制限-1:S.M.A.R.T.情報の誤動作により、ドライブの電源投入時間が5,184時間を超えると正常動作しなくなる不具合。
- 時間制限-2: 通電時間が累計で約5,000時間を超えるとシステムが異常終了し、再起動後も1時間ごとにクラッシュを繰り返す不具合。
- ファームウェアアップデート時の注意点: ファームウェアには不具合修正や性能向上のためのアップデートが存在しますが、アップデートに失敗するとSSDが故障するリスクがあります。ファームウェアアップデートを行う前に必ずデータのバックアップを取ることが推奨されます。
サンディスクのSSDからデータが消える問題
SanDiskのポータブルSSD「Extreme Pro」および「Extreme Pro V2」において、データが突然消失する、あるいはSSD自体が使用不能になるといった問題が2023年5月頃から報告されています。
データ復旧業者であるAttingoのマルクス・ハーフェレ氏は、この問題の原因をファームウェアではなく、設計および製造上の欠陥にあると指摘しています。 具体的には、はんだ付け工程で気泡が混入し、接合部が脆弱になっていることや、コンポーネントのサイズが基板上の設計と合わず、適切に接続されていないことが挙げられています。
これらの欠陥により、SSDが突然故障し、データ消失やデバイスの認識不良が発生する可能性があります。Western Digitalは問題を認識し、ファームウェアのアップデートを提供していますが、根本的な設計上の問題についての言及は避けています。 ユーザーは、重要なデータのバックアップを定期的に行い、問題が発生した場合は専門の業者に相談することが推奨されます。
物理的な障害
- 書き込み回数の上限およびデータ保存期間の限界: SSDはNANDフラッシュメモリを使用しているため、データの書き込み回数には制限があります。同一セルの書き換え回数は、SLCで約10万回、MLCで約1万回と言われています。また、データの保持期間も限られており、10年程度が目安とされています。
SSDのデフラグ
ハードディスクなどの記憶装置は長期間使用すると、データがディスク上で断片化し、アクセス速度が低下することがあります。この断片化を解消するために「デフラグ」を行いますが、SSDはその動作原理がハードディスクとは異なるため、デフラグは不要とされています。むしろ、SSDに対してデフラグを行うと、余計な書き込みが発生し、寿命が短くなる可能性があるため、OSのデフラグ機能はオフにしておくことが推奨されます。
ハードディスクは、ディスクの回転と読み取りヘッドのシーク時間が発生するため、データが断片化するとパフォーマンスが低下しやすいです。一方、SSDはフラッシュメモリに電気的にアクセスするため、原理的に断片化を解消してもほとんどメリットがありません。また、SSDには、データを適切に配置する仕組みがコントローラ上に備わっているため、そもそも断片化が起きにくいという特徴もあります。さらに、SSDにハードディスク用のデフラグツールを使用すると、書き換えが発生し、フラッシュメモリの寿命を縮めるリスクがあります。
Windows 7に搭載されているディスクデフラグツールは、SSDの使用を想定していないため、無効化することが推奨されています。しかし、Windows 8以降ではディスクデフラグツールの動作が変更されており、SSD使用時に無効化するとTrim機能も無効化されてしまいます。Trim機能が無効化されると、SSDの性能が十分に発揮できず、早期の故障につながる可能性があります。そのため、Windows 8以降のOSでは、ディスクデフラグツールを無効化しないことが推奨されています。OSのバージョンによってディスクデフラグツールの動作が異なるため、注意が必要です。