コンピュータウイルスの歴史
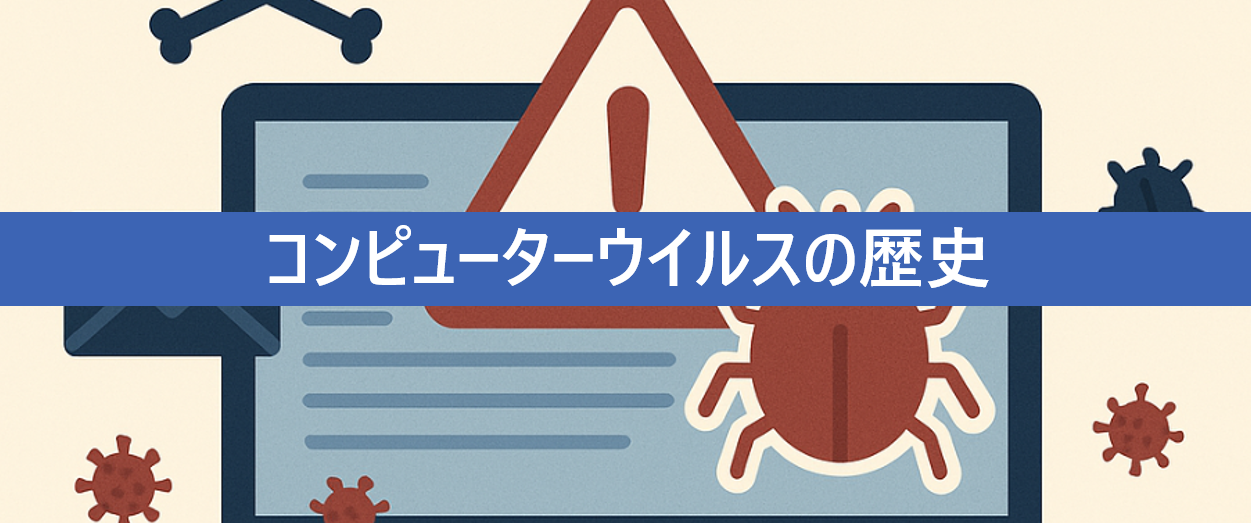
コンピュータウイルスとは
コンピュータウイルスとは、パソコンやスマートフォンをはじめとしたさまざまなコンピュータ上で動作し、日常的な操作や体験ができなくなるようにする悪意のあるプログラムを指します。
本来「ウイルス」とは、実際のウイルスと同様に自己増殖しながら感染を広げていく性質を持つものに限定される名称です。しかし近年では、このような増殖機能を持たない悪意あるプログラムも数多く存在します。そういった自己増殖しないタイプのプログラムは、本来であれば「マルウェア(悪意のあるソフトウェア全般)」というより広いカテゴリーに分類されます。
とはいえ、一般的にはマルウェア全体をまとめて「ウイルス」と呼ぶケースが多いため、本記事においても便宜上「ウイルス」という表現を使用します。
※コンピュータウイルスに関する詳細は、下記のページをご覧ください。
初期のコンピュータウイルス
コンピュータウイルスの起源は1940年代にジョン・フォン・ノイマンが提唱した自己複製プログラムの概念に遡ります。1970年代にはジョークプログラムが登場し、1982年には「Elk Cloner」がApple IIをターゲットにした最初のパソコンウイルスとして知られるようになりました。
パソコンをターゲットとしたウイルス
1986年、パキスタンで「Brain」というウイルスが開発され、IBM PCのブートセクタに感染し、フロッピーディスクを介して拡散しました。これにより不正コピー防止の役割も果たしました。
インターネットの普及とウイルスの拡大
1990年代後半には、インターネットの普及に伴い、ネットワーク経由で拡散するウイルスが増加しました。1999年には「Melissa」がOutlookを通じて広がり、企業や個人に大きな被害をもたらしました。2001年には「Code Red」がIIS(Internet Information Server)を標的にし、ボットネットを利用して大規模なDDoS攻撃を行いました。
ウイルスの目的の変化
2000年代になると、ウイルスの目的は愉快犯から利益追求にシフトしました。ファイル共有ソフト「Winny」や「Share」を通じて広がる「TROJ_MELLPON.A」や「山田ウイルス」は、ゾンビコンピュータを利用してボットネットを形成し、ボットハーダーが不正な活動を行いました。広告表示や国際電話の不正利用に加えて、アダルトサイトやビットコインの不正取得を目的とするウイルスも登場しました。
現代のウイルス
現代のウイルスは、キーロガーやランサムウェアなど、より高度な技術を駆使して金銭目的の攻撃を行います。スマートフォンやIoT機器もターゲットとなり、個人から企業まで幅広い対策が求められます。特にビットコインなどの暗号通貨を狙った攻撃が増加しており、セキュリティの重要性が一層高まっています。
ランサムウェア
ランサムウェアは、システムやデータを暗号化し、復号のための身代金を要求するウイルスです。特に企業や政府機関をターゲットにした攻撃が増加しており、大規模な被害をもたらしています。支払いにはビットコインなどの暗号通貨が利用されることが多いです。
キーロガー
キーロガーは、ユーザーのキーストロークを記録し、パスワードやクレジットカード情報を盗むウイルスです。これにより、金融詐欺や個人情報の流出が引き起こされます。
ウイルスを利用した攻撃では、安易なパスワードを設定しているアカウントがターゲットにされやすい傾向があります。加えて、複数のサービスで同じパスワードを使い回していると、被害にあう可能性がさらに高まります。パスワードの管理には十分注意を払いましょう。
スマートフォンおよびIoT機器
スマートフォンやIoT機器もウイルスの標的となっています。これらのデバイスには多くの個人情報が含まれており、セキュリティの脆弱性を突く攻撃が増えています。特にAndroidデバイスは、オープンなプラットフォームであるため、マルウェアのリスクが高いです。
ボットネットとDDoS攻撃
ボットネットは、感染したゾンビコンピュータを利用してDDoS攻撃を行います。これにより、特定のウェブサイトやサービスをダウンさせ、大規模な損害を与えることができます。ボットハーダーは、これらのボットネットを制御し、不正な活動を実行します。
暗号通貨マイニングマルウェア
最近では、ユーザーのコンピュータを利用して暗号通貨をマイニングするマルウェアも増加しています。これにより、システムのパフォーマンスが低下し、電力消費が増加します。
アダルトサイトを通じた感染
アダルトサイトは、マルウェアの拡散の温床となることが多いです。これらのサイトには悪意のある広告やリンクが含まれており、ユーザーがクリックすると感染するリスクがあります。
現代のウイルスは非常に高度化しており、対策としては信頼性の高いセキュリティソフトウェアの使用、定期的なシステムの更新、そして慎重なインターネットの利用が求められます。また、スマートフォンを利用しない方はインターネットユーザーにほとんどいないのではないでしょうか。スマートフォンのウイルスについて詳しく解説致します。
スマートフォンのウイルス
結論から申し上げるとiPhoneではほとんどの方がウィルス感染することはないです。一方でAndroidスマートフォンはさまざまなメーカーから開発されていることもあり、リスクが高いです。感染経路を認識することで防ぐことができます。
Androidデバイス
Androidデバイスはオープンなプラットフォームであるため、ウイルスやマルウェアの標的になりやすいです。Google Playストア以外の第三者のアプリストアからダウンロードしたアプリや、メールやメッセージのリンクを介して感染することが多いです。
iOSデバイス
iOSはクローズドなシステムであるため、ウイルスのリスクは比較的低いですが、全くないわけではありません。特に、脱獄(Jailbreak)されたデバイスはリスクが高まります。
感染経路
- アプリストア:信頼できないアプリストアからのアプリのダウンロード。
- メールやメッセージ:フィッシングメールや不審なメッセージのリンクをクリック。
- Wi-Fiネットワーク:公共のWi-Fiネットワークを利用する際のセキュリティリスク。
被害の種類
- 個人情報の漏洩:連絡先、メッセージ、位置情報などの個人情報が盗まれる。
- デバイスの操作:リモートでデバイスが操作される。
- 不正課金:アプリ内購入や通信料の不正請求。
対策
- 公式ストアからのダウンロード:アプリは公式のGoogle PlayストアやAppleのApp Storeからのみダウンロードする。
- セキュリティソフトの導入:信頼できるセキュリティソフトをインストールし、定期的にスキャンを行う。
- OSやアプリの更新:OSやアプリを常に最新の状態に保つ。
- 慎重なリンクのクリック:不審なリンクやメールは開かない。
スマートフォンは多くの個人情報を扱うため、セキュリティ対策が重要です。適切な対策を講じることで、ウイルス感染のリスクを大幅に減らすことができます。万が一ウイルスに感染し、データが破壊されてしまった場合でも、バックアップがあれば復元することが可能です。ただし、ウイルスによってはバックアップ先のHDDにまで被害を及ぼす可能性があるため、HDDはウイルス駆除を行った後に接続するようにしてください。